このコーナーでは、出産や育児をきっかけに立ち止まりながらも、自分らしい働き方を模索してきた女性たちの体験談をお聞きします。ママになってから、“ひとりの私”としての自分をあらためて問い直し、再構築していく——そんなストーリーをお届けします。
子育てが少し落ち着いたと思ったら、
今度は親の介護や義実家のこと、老後のことを考え始めるフェーズが訪れる。
「女性って、考えることが本当に多い。なのに、選択肢はどうしてこんなに少ないんだろう?」
そう感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
第4回のゲストは、「有機還元葬」の日本での実現を掲げ、「Deathフェス」や「nanowaプロジェクト」など多方面で活動する小野梨奈さん(以下、リナさん)。
「いまの“私”だからこそ、やるべきテーマだと思った」という言葉のなかに、“不自由な状況だからこそ生み出せる未来”のヒントがありました。

小野 梨奈さん
宇宙地球物理学を学び、サイエンスの知識を強みにIT・編集分野で活躍。産後は「フリーランス」という新しい女性の働き方を広める活動を行う。
現在は、死をより身近に考えられる場「Deathフェス」を企画し、日本での有機還元葬の実現を目指す「nanowaプロジェクト」などの活動を進めている。3児の母であり、趣味は卓球。
https://linktr.ee/onolina
https://x.com/onolina
https://www.instagram.com/onolina.earth
環境・故人・遺族をやさしくつなぐ「有機還元葬」とは
リナさんがいま“熱中”しているのは「有機還元葬」という新しい葬法。死をより身近に考えられる場「Deathフェス」などのイベントを通企画する傍らで、日本での実現に向けた活動を進めています。
有機還元葬(堆肥葬)とは?
有機還元葬(堆肥葬)は、簡単に言うと遺体を土に変える埋葬法。アメリカでは「ナチュラルでオーガニックな還元(Natural organic reduction)」と呼ばれ、遺体を自然な形で生分解して堆肥に変え、養分として新しい命へ循環させます。土葬と原理は同じですが、テクノロジーの力でより早く確実に土に還しています。
新しい埋葬の形。アメリカで注目の「有機還元葬(堆肥葬)」とは? | ライフスタイル | サステナブルに暮らしを楽しむ情報・アイデア Life Hugger
 彩
彩どうして、リナさんはいま有機還元葬に“熱中”しているのでしょうか?



私自身が「これすごくいい! 選びたい!」と思ったこと。
そして、これからの時代に必要な選択肢だと直感で思ったからです。
リナ:有機還元葬のことを知ったときに、「私はこれを選びたい!」と思いました。日本でもできるのかな?といろいろ調べていくと、死の周辺にはさまざまな社会課題があることがわかりました。社会全体が「多死社会」に入り、これまでの慣習や文化を引き継ぎつつも、時代にあった葬送の選択肢をアップデートする必要なのではないかと感じました。
まわりで親の介護やお墓の話題を聞くことも増え、
「このままの仕組みを子どもたちの世代に引き継ぐのは違うのでは」と思いました。
私がずっと大切にしてきたテーマのひとつが、
自分にフィットするものがなければ、新しい選択肢をつくるということです。
それまで、火葬があたりまえだと思い込んでいたけれども、世界ではそれ以外の選択肢があり、より環境にやさしい方法も選べるんだと知り、なぜ日本で選べないのだろう? 選べるようにしなくちゃ!と思ってしまって。
もともと私はサイエンスやサステナビリティといったテーマにも関心がありました。今までやってきたことを繋ぎ合わせて考えたとき、「有機還元葬」というテーマに自然とつながっていったのだと思います。
これまでの経験がすべて凝縮されていて、自分の強みを活かせる。
そんな感覚もあって、「これはもう、私がやるべきテーマだ」と思いました(笑)。



「選択肢が少ないなら、作ればいい」という発想が、シンプルで力強いですね!
どうしたら自分のやりたいことを続けられるか?



育児をしながら複数の仕事を続けるのって本当に大変ですよね。どうやって続けてこられたんですか?



私は「ずっと働き続けたい」と思っていたんです。
リナ:母子家庭で育ったので、女性も自分で稼ぎ、自立しなければ、という思いが強いかもしれません。私が社会人になった当時は、結婚や出産で退職する人がまだ多い時代でしたが、私は“仕事も子育ても趣味も全部同時進行に楽しみたいタイプ”で。会社員の働き方だとそれは難しく、だからこそ、当時はフリーランスという働き方が自分にすごく合っていると感じました。
子どもが小さい頃は、夫が残業で帰りが遅く、私は夕方に一度仕事を切り上げて終えて、夜に再開する生活でした。心の中にはいつも「もっと働きたい」という気持ちがありました。
子育て中でも、仕事量を少しずつ調整しながら、なんとか大好きな仕事を手放さずに続けてきました。
その経験があったからこそ、この働き方をもっと多くの人に知ってほしいと思ったんです。
そうすれば、より多くの女性が無理なく働けるようになる。そんな新しい選択肢を広めたいと考えていました。



産後は「女性フリーランス」というテーマ、そして今は「有機還元葬」に“熱中”しているんですね。どの時期でも軸がブレないのが本当にすごいです。
大きな挑戦を続けるには、“自分を知ること”から



「有機還元葬」の実現には法律など多くのハードルがありますよね。そんな大きな挑戦に向かうとき、「本当にできるのかな…」と怖くなったり不安を感じることはありますか?



「本当にできるのかな…」と思うことは時々あります。
でも、そういうときって大抵“疲れている時”なんですよね。だから無理せず休むようにしています。
リナ:諦めたらそれで終わりだけど、諦めずに続けていれば、必ず誰かが見てくれているし、思うように進まないことがあっても、やめずに続けていけば、きっと形になる。
“諦めなければ叶う”という感覚は、子どもの頃からの小さな成功体験の積み重ねかもしれません。
たとえば昔、ウェブメディアの編集の仕事をしたくて編集長に手紙を書いたことがありました。その時は採用されなかったけれど、後日また募集が出た時に声をかけてもらえて、憧れの仕事につけたんです。
だから私は、“今できる小さなアクション”を続けることを大切にしています。
彩:リナさんって、いつも迷いがなさそうに見えますが、自分の状態をちゃんと把握してるから不安を引きずらないんですね。
リナ:疲れているときは、何もかもネガティブに見えてしまいますよね。
でも、自分のパターンを知ってからは、うまくいかない時期も前向きに受け止められるようになりました。
私は要領がいいタイプではなくて、不器用なんです。でも、これだと思ったことをコツコツ努力するのは得意。
ただし、それには“確固たるテーマ”が必要で、そのテーマに“熱中”できるかどうかが大事なんです。
「時間はかかっても、コツコツ続けていけばきっとできる」——
そう信じられるようになったのは、これまでの経験のおかげかもしれません。



リナさんの強さは、ブレずに続けられる情熱と、自分のペースや成功パターンを理解しているロジカルさの両方を持っているところなんですね。
何事も“熱”が冷めないうちに。行動でチャンスと仲間をつかむ



共同代表の市川のぞみさんに有機還元葬の話をしたことが、「Deathフェス」につながったと伺いました。そこからどうやって心強い仲間として関係が深まっていったのでしょうか?



きっかけは、たまたまの会話でしたが、“熱”が冷めないうちにすぐにアクションはしました。
リナ:ワーケーションで行った長野で、夜にお酒を飲みながら話していた時に、「実は有機還元葬っていうのがあって…」と、軽い気持ちで話したのがきっかけでした。
そしたら、のぞみさんが「それ、すごくいいね!」って言ってくれて、一気に盛り上がって。
でも、そういう時ってたいてい“その場のノリで終わる”ことが多いじゃないですか。
だから私は「これは絶対に形にしたい」と思って、すぐにアイディアマップをまとめてのぞみさんに送りました。
彩:なるほど、すぐに後押しのアプローチをしたんですね。
リナ:そう。勢いがあるうちに動かないと、熱量ってすぐ冷めてしまうので。
あの時は、「いま、形にしなきゃもったいない」と思ったんです。その後、のそみざんがETICのBeyondersというプロジェクトがあるのを教えてくれて、それに応募し、結果的に、「Deathフェス」という企画につながりました。
そこからは本当にトントン拍子に進んでいきました。
動いていたのは私たち二人だけど、「今これが必要だよね」という社会の流れや人々の意識、そうした“言葉にできない力”にも背中を押されている気がします。スピリチュアルな意味ではなく(笑)。



その場のノリで終わらせず、“行動”でチャンスと仲間をつかんだんですね!
死と向き合うことで見えてきた“日常のなかの大切なもの”



死や命と深く向き合うからこそ、日常や子育てで大切にしていることはありますか?



うーん、どうだろう。
子育てで意識しているのは、自分が“熱中してもがいている姿”を子どもに見せることです。
好きなことに一生懸命打ち込んで、うまくいかなくても挑戦して、それでも楽しそうに頑張っている——
そういう姿を見せたいなと思っています。
家族がどう思っているのかは……そういえば聞いたことがないですね(笑)。
でも、いつもあたたかく応援してくれています。
あとは本当に小さなことですが、「人はいつ最期をむかえるのか」は分からない、という感覚が以前よりも強くなりました。
「朝出かけて、そのまま帰ってこなかった」という話も本当にあるんですよね。
だから、家族が出かける時は必ず玄関で顔を見て、「いってらっしゃい」と声をかけるようにしています。
彩:「いってらっしゃい」って、当たり前のようでいて、意識していないとつい忘れてしまうことも多いですよね。私も、つい「明日もまた会える」と思い込んでしまうので、見習おうと思いました。



「いってらっしゃい」が言える時間こそ、実はすごく大切なんですよね。
行動した先の出会いが未来を縫い合わせる



子育てに一区切りがつき始めて、これからの自分に迷うママへ、メッセージをお願いします。



やってみたいことがあるならまずはやってみて、会いたい人には会いに行ってみてほしいです。
やってみたいことがあれば、とりあえずやってみて
リナ:多くの人が「ちゃんと準備してから」と思いがちだけど、それを待っていたら動けない。少しフライングでもいいから、まずは動く。
そうすると、うまくいかない部分が見えてきて、「じゃあ次はこうしてみよう」と改善できる。行動を重ねるうちに、自然と形になっていくものだと思います。
会いたい人には、会いに行ってみて
リナ:「会いたい人には会いに行く」ことも大事にしています。
私は知らない人に連絡するのが怖くないタイプで、気になる人がいたら割とガンガン会いにいきます(笑)。
でも、広く浅く関わるより、少人数でじっくり話して関係を深める方が好きなんです。無理に交流会に行くよりも、自分に合った形で人とつながるほうが心地いいですね。
私は広げるのは苦手かもしれないけど。そういうやりかたで、繋がりの関係性を作っていけばいいんじゃないかなって。



リナさんがそうして関係を丁寧に育ててきたからこそ、のぞみさんのようなパートナーに出会えたのかもしれないですね。
いまの“私”だからこそ、できることとは?
「子育てと仕事の両立」という言葉をよく耳にします。私自身も、何度もその言葉を頭の中で繰り返してきました。
結婚、出産、育児、介護——。
女性は人生のフェーズが多いからこそ、「子育てと仕事の両立」がいつの間にか“目的”になってしまうことがあります。
ですが、リナさんの話を聞いていると、
大切なのは“両立”ではなく、「やりたいことをどう続けていくか」。
そして、選択肢が少ないと感じたなら「自分で選択肢をつくればいい」。
その発想こそ、“私”らしく生きるヒントなのだと思いました。
そのためには、自分の“いま”を丁寧に見つめること。
——どんな状態にあるのか。
——何に心が動いているのか。
——誰に会いたいのか。
——いまできることは何か。
もし今、「挑戦したい」「興味がある」と思っているのに時間や自由がないと感じている人がいたら——
“いまの私だからこそ、できることは何か?”
そう問いかけてみてください。
リナさん、ありがとうございました!


女性だからこそ気になる「自分の死」について
リナさんは「女性のほうが、死について考えることが多いと思う」と話してくれました。
いまは子育てに追われて考える余裕がなくても、ふと“その先”の人生を思うとき、新しい選択肢が見えてくるかもしれません。
リナさんは毎年「Deathフェス」や「渋谷でDeathラジオ」など、死をもっとカジュアルに考えるきっかけを作るために様々な取り組みを続けています。
- 義実家のお墓に入ることに、なんとなく違和感がある
- 子どもに「墓守」などの負担を背負わせたくない
- もし火葬以外の選択肢があるなら、選んでみたい
もし、上記のどれかひとつでも心に響いたなら、一度リナさんのイベントに足を運んでみてはいかがでしょうか。

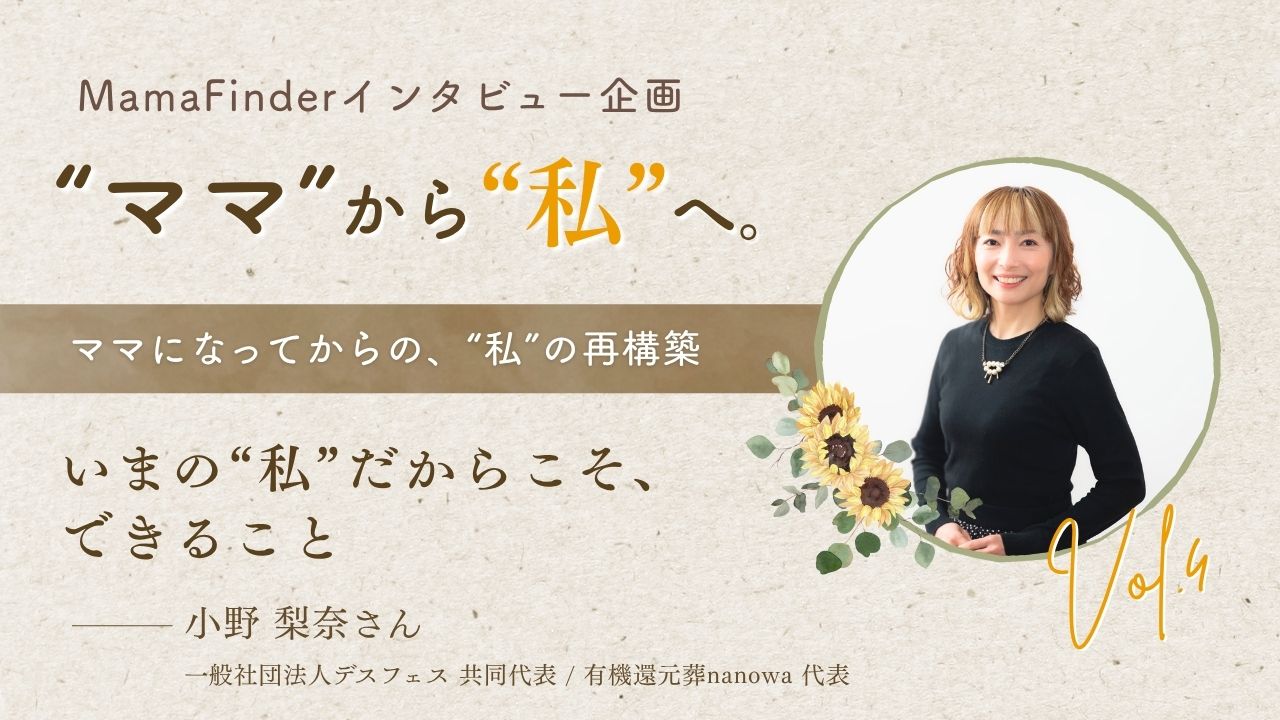
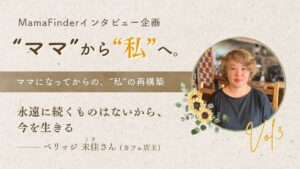




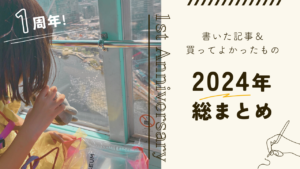
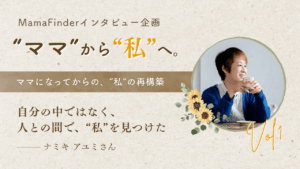


グッズの口コミ・育児体験を書く