「療育」や「ことばの教室」という、子どもの発達をサポートするサービスをご存知でしょうか?
名前は聞いたことがあるけれど、「どんなことをするの?」「うちの子も通えるの?」 と、具体的な内容がよく分からないという方も多いかもしれません。
特に療育は、施設によって取り組む内容が大きく異なります。
「親子同室タイプ」「預かりタイプ」 などの違いがあるほか、ことば・運動・生活スキルなど、力を入れる分野がそれぞれ異なるため、一言で「療育」といってもその形態はさまざまです。
そこで今回、療育やことばの教室を実際に利用した方にインタビューを行い、リアルな体験談を伺いました!
「興味はあるけど迷っている…」という方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。
療育・ことばの教室について
療育(発達支援)とは
療育とは、障害のある子どもやその可能性がある子ども(0〜未就学児)が利用できる通所支援サービスです。子どもの障害特性や発達状況に合わせて、困りごとの解決や将来の自立などを目指して支援・サポートを受けることができます。
より詳しく知りたい方は、以下の記事にまとめましたので、ご参考にどうぞ!

ことばの教室とは
ことばの教室とは、発音や言葉の発達に課題がある子どもを対象に、専門的な支援を受けられる教育機関です。主に自治体の発達支援センターや学校内に設置されており、言語聴覚士(ST)や特別支援教育の専門家が指導を行います。
発音のクセや言葉の遅れ、コミュニケーションのしづらさなど、子どもの言葉に関する困りごとに対し、発音の練習や語彙の強化、聞く・話す力のトレーニングを通じてサポートします。
参考サイト:
- LITALICO発達ナビ:「ことばの教室とは?どんな支援が受けられるの?通級、支援級の違いは?」 h-navi.jp
- 千葉県総合教育センター:「ことばの教室(言語通級指導教室)の概要」 ice.or.jp
- 富良野市:「ことばの教室とは」 city.furano.hokkaido.jp
- 練馬区:「区立小学校に設置している言語障害学級(ことばの教室)について」 city.nerima.tokyo.jp
今回紹介する3つの事例
 彩
彩預かりタイプ(※)の療育を利用中の6歳女の子ママ。4歳の頃に娘の登園しぶりに悩み、自ら療育を利用し始めた。
半預かりタイプ(※)の療育を利用中の6歳男の子ママ。3歳頃に保育園の巡回相談で児童発達支援士の方の勧めを受けて療育を利用し始めた。
ことばの教室を利用中の5歳男の子ママ。発音のトレーニングが必要だった息子のために教育相談室に通い始めた。
※療育施設には「預かりタイプ」「親子同室タイプ」など、預かり時間により種類が分かれます。詳しくは以下の記事に記載しています!
【預かりタイプの療育】を利用した彩のエピソード



娘の新たな一面を発見!心が安定し、親子のコミュニケーションが増えました
通い始めたきっかけ
娘は1歳半健診でことばの遅れを指摘され、発達支援センター(※)に通っていましたが、その後は「様子を見ましょう」と言われていました。
しかし、4歳の頃から登園しぶりが激しくなり、娘もうまく理由を言葉にできず、親子ともに疲弊。調べるうちに診断がなくても療育サービスを利用できると知り、受給者証を取得して療育を開始しました。
※子どもの発達の遅れや生活の困りごとに対し、専門家が相談・療育を行う支援機関
施設の特徴・活動内容・頻度
娘は週1回、4時間、療育施設で過ごした後、保育園に送迎してもらっています。利用している施設は民間ですが、受給者証を使えるため公的な療育施設と同様に費用補助が受けられます。
施設では運動や作業療法のほか、言語療育も併用。言語聴覚士(ST)の先生と1対1で会話の練習をし、表現力やコミュニケーション力をサポートしてもらっています。
通い始めて感じた変化
私は仕事を詰め込みがちで、療育を利用する前は平日は娘との時間が不足しがちでしたが、療育を始めたことで週1は仕事量を調整する決心ができました。毎回のお弁当作りは大変だなと感じることもありますが、お弁当作りを通して親子のコミュニケーションが増えました。
また、娘の居場所が増えたことで、新たな一面を知る機会が増えました。家では甘えん坊な娘が、施設ではとても真面目で頑張り屋さんだったことに驚き、「登園しぶりはただのイヤイヤではなく、頑張りすぎて心が疲れていたSOSだったのかもしれない」と気づくことができました。
療育を利用し始めてから、登園しぶりが少しずつ落ち着き、娘の気持ちも安定してきました。
利用を検討している方へのメッセージ
「診断がないのに療育を利用していいの?」と迷いましたが、結果的に娘を知ってくれる人や相談できる場所が増えたことは大きな支えになりました。
育児の悩みを抱えているママさんにとって、療育が新たな選択肢になればと思います。それが結果的に、「子どもが安心して過ごせる居場所づくり」にもつながるのではないでしょうか。
【半預かりタイプの療育】を利用したMさんのエピソード
困りごとが分かれば、対処法も見えてくる。子どもの自立のきっかけになりました!
通い始めたきっかけ
1歳半健診で「発達がゆっくり」と言われていましたが、当時は様子見の状態でした。その後、3歳頃に保育園の巡回相談を利用したところ、児童発達支援士の方の勧めで発達検査を受けました。
当時の息子は、運動会や発表会などの行事で泣いてしまったり、動けなくなってしまったりといった困りごとを抱えていました。
発達検査を受けた後は、児童発達支援士さんが施設の選定や予約などをサポートしてくれたため、スムーズに療育を利用することができました。ただ、利用開始までには待ち時間があり、療育を決めてから実際に通えるようになるまで約半年 かかりました。
施設の特徴・活動内容・頻度
施設には週1回、2時間ほど通っています。親子で一緒に通いますが、療育は子どもだけで行い、親は別室で待機するスタイルです。そのため、「親子同室タイプ」と「預かりタイプ」の中間のような施設とも言えるかもしれません。
息子は予定外のことが苦手で、ルーティンがあると安心できるタイプ。そのため、通っている施設もそういった特性に配慮した工夫がされています。たとえば、活動内容は毎回変わるのではなく、1ヶ月ごとに変化するように設定されていたり、事前に活動内容をイラストなどで視覚化して子どもにわかりやすく伝えてくれる などの工夫がされています。
また、別室で待機するスタイルは、親にとってもメリットが多いと感じました。療育内容のひとつであるクッキングでは、子どもが作った料理を親子で一緒に食べたりもできるし、保護者同士が交流する機会にもなります。
通い始めて感じた変化
通い始めて半年ほどで、大きな変化 を感じました。最初は息子は保育園でお友達と遊ぶよりもひとり遊びをすることが多かったのですが、いまでは泣いているお友達に「どうしたの?」と声をかけるなど、他の子と関わろうとしたり、一緒に楽しく遊べるようになりました。
少人数の環境での療育を通して、人との関わり方や気持ちの伝え方を学んだことで、保育園などの集団生活でも少しずつ「どう振る舞えばいいのか」が分かるようになってきたのではないかと思います。以前は泣いてしまっていた行事にも、自分から楽しんで参加できるようになました。
ここまで成長できたのは、療育を利用していなかったら難しかったかもしれません。通わせて本当によかったと実感しています。
利用を検討している方へのメッセージ
療育は、実際に利用できるまでに時間がかかることが多いため、気になったら早めに動くことをおすすめします!
また、私の利用している施設では親同士の交流の場もありました。同じように悩みを抱えるママたちと話したり、先輩ママから情報を聞けたりすることで、子どもだけでなく親にとっても貴重な場所になっています。子育ての悩みを、身近な人に話せる環境があることは本当に大事だと感じました。
自治体の担当者によって対応が違うこともあるため、実際に療育を利用している保護者の方の話を聞くのが、一番参考になるのではないかと思います。
【ことばの教室】を利用したRさんのエピソード
「できないことも、練習すればできる」という自信が息子に生まれました!
通い始めたきっかけ
息子は小さく生まれ、「発音や運動面の発達がゆっくり」と言われていました。小児科で経過を見ていたところ、先生から「発音の練習が必要」と勧められ、ことばの教室を利用することにしました。
当時の息子は「さ行(さしすせそ)」を「は行(はひふへほ)」に置き換えてしまうことがあり、発音に課題を感じていました。私は療育に関わる仕事をしているため、不安や抵抗はなく、「支援の場につながれた」安心感のほうが大きかったです。
施設の特徴・活動内容・頻度
息子と一緒に教育相談室(※)のことばの教室に月1〜2回、1回30分程度通っています。ここでは「構音(こうおん)訓練」と呼ばれる発音のトレーニングを行い、息の出し方や舌の使い方を練習します。先生が「こういう口の形にすると『す』が言いやすいよ」などと優しく声をかけながら指導してくれるため、息子も楽しく学んでいます。
また、教室で学んだことを家庭でも続けられるように、宿題が出されます。飽きないように、例えば「す」の練習なら「すいか」「すいとう」など、身近なものを探すゲーム感覚で楽しみながら続ける工夫をしています。
通い始めて感じた変化
以前は「この音は言えない」と気にしていた息子ですが、少しずつ発音できるようになり、嬉しそうな表情を見せることが増えました。まだ言えない音もありますが、「練習すればできるようになる」 という前向きな気持ちで取り組めるようになったのは大きな変化です。
利用を検討している方へのメッセージ
ことばの教室や療育というと、「特別な支援が必要な子が通う場所」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、風邪を引いたら小児科に行くのと同じように、ことばの発達をサポートする場所があるのは自然なことだと思います。
「特別なこと」と構えず、「我が子が成長できる場」として気軽に利用できる人が増えたら嬉しいなと思います。
豆知識:教育相談室とは?発達支援センターと違うの?
教育相談室とは
教育相談室は、学校生活や発達の悩みについて、保護者や本人が相談できる自治体の窓口です。不登校や学習の遅れ、友人関係の悩みなど、教育の視点からサポートを行い、必要に応じて発達検査や支援機関の紹介をします。
基本的に、相談はどちらも無料です。ただし、自治体によって役割が少し違うこともあるので、実際に利用するときは自治体のHPでご確認ください。
発達支援センターとの違い
| 教育相談室 | 発達支援センター | |
|---|---|---|
| 対象 | 就学前〜高校生 | 乳幼児〜小学生 |
| 相談内容 | 学習の遅れ、不登校、友人関係 | 言葉・運動の遅れ、発達の困りごと |
| 支援方法 | 相談・アドバイス、機関の紹介 | 療育・発達支援プログラム |
引用元:
教育相談室 江戸川区ホームページ
教育相談とは?相談の流れ、申し込み方法など【専門家監修】【LITALICO発達ナビ】
さいごに
「発達支援」と一言でいっても、親子によって悩みや必要なサポートはさまざま。
今回の3つの事例からも、「困りごと」も「利用の仕方」もそれぞれ違う ことがわかりました。
もし、子どもの発達や育児のことで悩んでいるなら、一度、市の発達相談窓口や発達支援を行っている小児科に相談してみるのもひとつの方法です。専門家に話すことで、「どんなサポートが合うのか」や「どこに相談すればいいのか」などのヒントが得られる かもしれません。
また、今回のインタビューで共通していたのは、療育やことばの教室を利用するまでに時間がかかる という点でした。申し込みをしてから実際に利用できるまでに、数ヶ月〜半年以上待つことも珍しくありません。
その間に、「本当に通わせるべき?」と迷ったり、親のモチベーションが下がったりすることもある かもしれません。
でも、実際に通ったママたちはみんな、「療育やことばの教室を利用してよかった」と感じています。
「気になったら、まずは一歩踏み出してみること」。
それが、後になって「やってよかった」と思えるきっかけになるかもしれません。
この記事が、子どもの発達や育児の悩みを抱えるママにとって、少しでもヒントや後押しになれば嬉しいです。






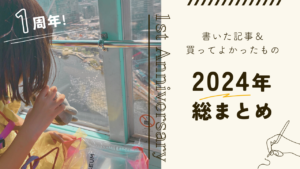
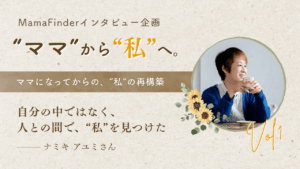


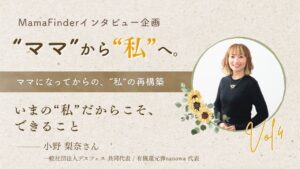


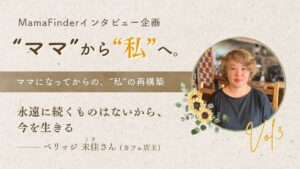

グッズの口コミ・育児体験を書く